臨月に入って、これまで大切にしてきた子育てに関する本を3つ、読み返してみました。
わたしは読み終わった本は手放してしまうことが多くて、手元に置いてある方が珍しいくらいなのですが、手放せなかった本を改めて読むと、内容を知っているのに とても新鮮な気持ちに。
そこで感じたことなど、まとめてみました。
脳科学からみた 8歳までの子どもの脳にやっていいこと 悪いこと
『早寝・早起き・朝ごはん』
このシンプルさがいいなあと思って、大切にしてきた一冊。
たっぷり眠れて、自然と目が覚めて、美味しくご飯が食べられる。これさえできれば、とりあえずはオッケーだということが書かれています。
誰もが気軽に発信できる時代なので、巷には子どもと子育てに関する情報が溢れすぎていて、何が正解?そんなに上手くできないよ~と、迷子になっていたところ、出会ったのがこの一冊でした。そこからは何を聞いても、迷ったらまずここへ立ち戻るようになりました。
『早寝・早起き・朝ごはん』については、こうすると良いですよ、という具体的なアドバイスが 根拠をもとに書かれていて、あとは朝日をしっかり浴びようとか、親子での会話を大切に、など、当たり前のことだけど、忙しい日々のなかでうっかり見落としてしまいそうな、大切なことがぎゅっ詰まっています。
0歳の今すべきこと!とか、将来子どもの役に立つ 〇選!というような強いメッセージに引っ張られそうになるけれど、まずは一日一日を丁寧に過ごすこと、そんなに焦らなくても大丈夫、と冷静になれる、 お守りのような一冊。薄い本だけど、何度読み返しても、そのたびに『あの時のあれは、そういうことだったのか...!』と腑に落ちるような気付きがあって、この本に出会えてよかったと思います。
私たちは子どもに何ができるのか
『非認知能力』という言葉があることを知って 読んでみようと思った一冊なのですが、わたしにとっては、非認知能力 云々よりも、未来ある子ども達に対する大人の責任の重さ。そんなことを突き付けられたような、衝撃を受けた本。最初に読んだときの感情を忘れたくなくて、手元に残しているという一冊です。
まず冒頭の『まえがき』が かなりショッキング。非認知能力の大切さと、子ども自身にはどうしようもなく、それを奪ってしまう環境というものがある現実に、ガーンと頭を打たれたような、衝撃を覚えています。(初めて読んだのが出産直前だったということもあり。。)
子ども自身には育つ力がある、子どもは大人から与えるられるだけの弱い存在ではない、という側面も もちろんあると思いますが、この本を読むとタイトルのとおり『わたしは子どもに何ができるんだろう』そんなことを思います。
家族そろってぐっすり眠れる 医者が教える赤ちゃん快眠メソッド
これは第一子のときに読んではいたけれど、活かせなかった一冊。二人目ベビーには最初から『ネントレ』ができたらいいなあと思っていて、読み返しました。
親が添い寝して、ウトウト、スーッと夢の中...
子育てをする前も、始まった後も、一日の終わりの親子の温かい時間=『子どもの寝かしつけ』というのが理想。それに対してネントレは、なんだかアッサリしているというか、ほんとに大丈夫なのかな、という疑問があって、どうしても踏み出せませんでした。。
だけど、もうすぐ 3歳になる子どもを実際に寝かしつけていると、理想通りに行く日なんて、数えるほど。親の隣で微笑みながらスーッと夢の中 なんて、もはやフィクションよ~。
この頃はお布団に入ると、うたを歌い始めたり、おしゃべり止まらなくなったり、しまいには眠たいのに寝れずにグズグズ泣き始めたり。上手く眠れる日もあるけれど、眠れない日との差が激しくて、これは子どもにとっても辛いことなのではと思い始めました。(もちろん親もツラい。。)やっぱりネントレしておけばよかったかなーと思う日もしばしば。
寝かしつけに1時間、2時間かかるとき、自分事に置き換えて考えると、寝たいけど寝れなくて、何時間も布団の中に居なきゃいけないって、たぶん本人もつらい。
ネントレは月齢が小さいほど上手くいくようなので、スイッチが切りかわるようにパチンっと眠れるようになればいいなあと、いまから予習をしています。そして二人でスッと寝てくれる日がいつか来ると信じて。。
おわりに

手探りの中で子育てをしていて、なにか引っかかる、これはわたしにとって大事な一冊になるのではないかと思って手元に残していた本。3年経ってもそれは変わらないので、子育てにおいては自分の中にあるものと照らし合わせてしっくりくる、という感覚は大事なのかも。
二人目、といっても親としてはまだまだなので、この3冊を大切にしつつ、なにか新しいことも取り入れていけたらいいなあと、そんなことを考えている残り少ないマタニティーライフです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました♩
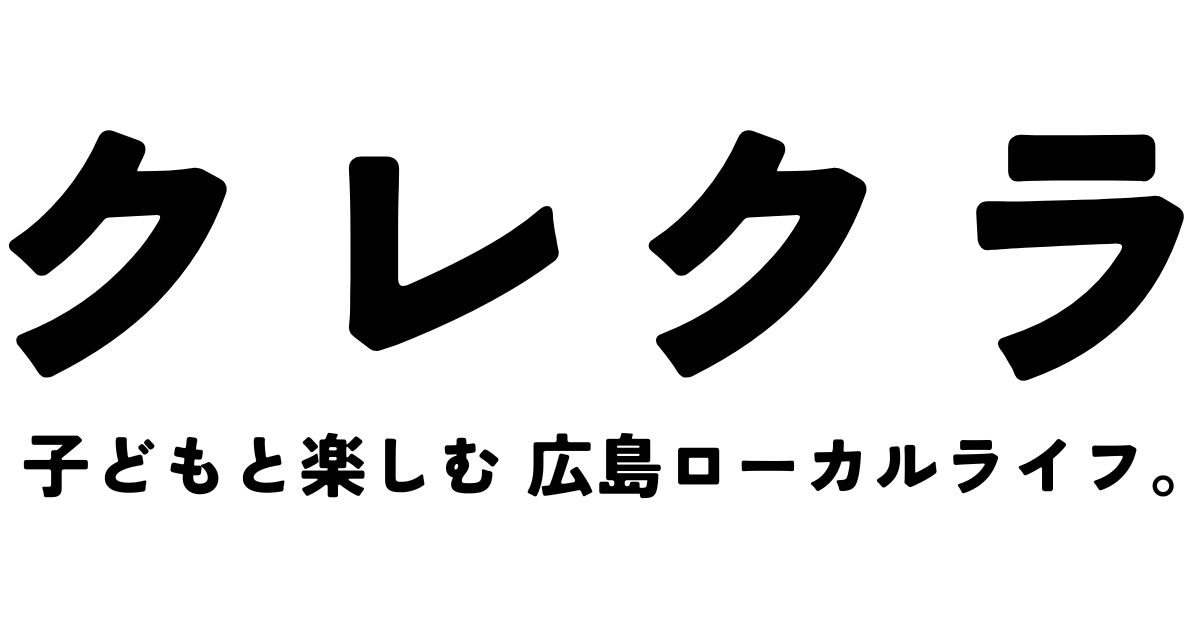
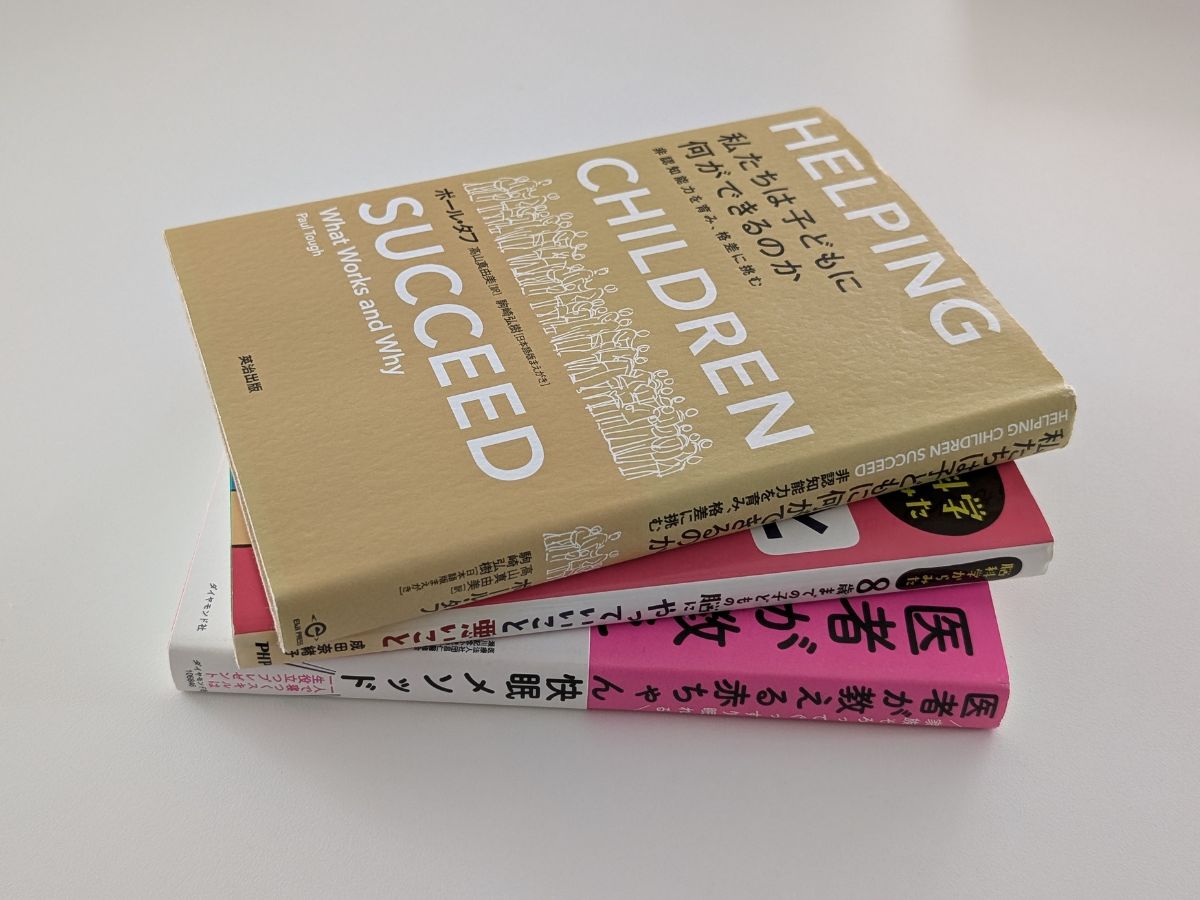








コメント